
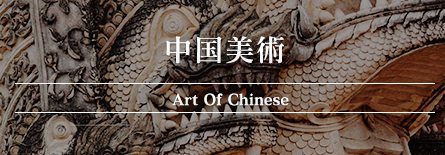
これから中国美術について知っていきたい人から、趣味にしたい人まで。中国美術を学びたい人のためのサイトです。
時代、ジャンル、中国美術を極めたい人向けの記事を豊富に用意しております。あなたが中国美術に触れる際の、お役に立てる入門書となりますように。
このサイトは本郷美術骨董館をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
青磁についての基礎知識を説明していきます。
青磁は中国で発展した陶磁器で、その歴史は殷の時代にさかのぼります。殷の時代は灰釉が使われており、龍窯が進歩するにしたがって、良質な青磁が生産されるようになりました。なお、灰釉と青磁釉の中間的な釉をもつ陶磁器は「原始青磁」「初期青磁」と呼ばれています。いわゆる「青磁」とされる釉が現れたのは後漢~西晋時代。越州窯(浙江省)で生産された青磁が良く知られています。
唐代以降、青磁は文人や知識人を中心に愛でられました。それは青磁が「碧玉」や「ヒスイ」に近い色だったからです。古代よりこれらの宝玉は「君子が身に付けるもの」であり、儒教においては「徳の根源」として尊重されていたことから、「假玉器」とも呼ばれた青磁は上流階級の貴族や文人にもてはやされたと考えられています。
青磁とは、薄っすらとした青や緑の発色を特徴とした陶磁器のこと。ただし、青色や緑色を帯びた陶磁器はたくさんありますが、それらの全てが青磁というわけではありません。
厳密な意味における青磁とは、切開にわずかな酸化鉄を混ぜて作られた釉(うわぐすり)を塗って焼き上げる陶磁器。酸素を量を制限しながら焼き上げることで、絶妙な青色・緑色の発色が生まれます。わずかな条件の違いで発色に差が生まれますが、この発色の質や差を鑑賞することが、まずは青磁の魅力の一つと言って良いでしょう。
また、後述しますが「貫入(かんにゅう)」の入り方も青磁の魅力の一つ。「貫入」とは、様々な陶磁器に見られる細かいヒビのことですが、青磁の「貫入」は特に細かく特徴的で、青磁の美しさ全体を左右する大事な要素とされています。これら「発色」と「貫入」が、青磁の魅力のポイントであり、かつ鑑賞や批評の対象と考えてください。
なお、時代の変化により、また長年の試行錯誤により、現代では多種多様な青磁が市場に流通しています。種類が多様だからこそ、年齢や人生経験、趣向などに合わせて様々な作品を味わうことができます。その点も、現代の青磁の魅力の一つかもしれません。
青磁が美しい青に発色するのは、器の表面を覆う「釉薬」に秘密があります。釉薬というのは、植物の灰を溶いた液体に、「長石」の粉を混ぜたもの。高い温度で焼くとガラス質に変わり、器に強度、色やツヤを与えるのです。青磁制作に使われる釉薬には、わずかに鉄が含まれており、それを焼成すると独特な風合いの青になります。とはいえ、釉薬だけで必ず青磁ができるわけでありません。
青磁を作るのには「還元炎焼成」を行います。これは「窯内への酸素を制限し、焼成物から酸素を奪う」焚き方で、この方法で焼成すると、釉薬に含まれる酸素が燃焼に使われます。通常、焼いた鉄は「酸化炎焼成(窯内に十分酸素を供給する焚き方)」により赤茶色に発色しますが、釉薬の中の酸素が還元され、青い色になるわけです。
また青磁の特徴として「貫入」があります。これは簡単にいうと「ひび」のこと。白磁・青花(染付)・五彩(色絵)といった他のやきものにも見られますが、特に、青磁の場合、全体の青と細かいひびが生み出す独特の景色が、鑑賞の対象になってきました。
貫入は、胎土(磁土)に比較して釉薬の収縮率が大きい場合、焼成後の冷却時に起こります。特に青磁は何回も釉を重ねて焼成するため、貫入が起こりやすくなるのです。なお、貫入には色が付いているものや無色のものがありますが、焼き上がった直後に墨汁に漬けるなど、さまざまな技法が用いられています。
近年、宮廷向けに作られた青磁が日本で確認されました。淡い青色をしており、その美しさは現代でも多くの人々の心を動かしています。青磁の中でも、汝窯青磁は最高蜂ともいわれるほどの品で、世界に90点しかなく、国内では3点目となる青磁の作品となります。
今回確認されたのは酒や茶を入れる盞と言われるもので高さ5・2センチ、最大直径10・2センチの小さな茶碗でした。青磁は、2012年に香港のオークションで約23億円という高額な値段で落札されたこともある、大変有名な骨董品なのです。
悲しいことに、有名作家の青磁でニセモノの骨董品が出回っているケースが後を絶ちません。一般的な知識しか持っていない人にとって、本物とニセモノの見分け方は難しいといわれています。
また、ニセモノは光沢感がありすぎるものや絵が雑に描かれているものがほとんどなので、作品を見て少しでも違和感があればニセモノの可能性があります。
しかし、ニセモノでも本物とそっくりな品もありますので、一目見て判断するのは難しいのも事実です。確実に本物かニセモノか見分けるためには鑑定士に見てもらう必要があります。
監修本郷美術骨董館

「やさしく解説!みんなの中国美術入門」は、骨董品買取の専門店として40年以上の実績を誇る本郷美術骨董館が監修しています。
公式HPはこちら