
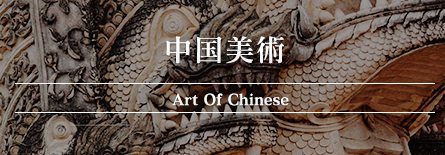
これから中国美術について知っていきたい人から、趣味にしたい人まで。中国美術を学びたい人のためのサイトです。
時代、ジャンル、中国美術を極めたい人向けの記事を豊富に用意しております。あなたが中国美術に触れる際の、お役に立てる入門書となりますように。
このサイトは本郷美術骨董館をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
秦・漢時代の中国美術に関して解説していきます。

殷を倒し、「建制体制」を築き、孔子をはじめ、多くの儒学家に「礼の理念で統治された理想的な時代」と称された周王朝。しかし、前9世紀になると異民族の侵入、諸侯の反乱などが起こり、周の権威は次第に弱まっていきます。
そんな中、前770年、犬戎(北方の遊牧民)が周の幽王を殺害。諸侯に助けられた周王室の一人が平王となり、洛陽に「東周」を再建します。とはいえ、周の王権はすっかり衰え、前5世紀末になると有名無実化。やがて「戦国の七雄」が覇を争う「春秋・戦国時代(前770年~前403年を春秋、これ以降、前221年までを戦国と分類)」に突入します
中国を分割支配したのは、韓、魏、趙、斉、燕、楚、秦の7国で、ほかにも魯、衛、宋などの小国も含め、互いに争い、権謀術数を繰り返していました。混沌とした状況の中、ライバル国を滅ぼし、前221年、初めて中国を統一したのが秦の始皇帝です。
始皇帝は郡県制の採用をはじめ、それまで国内が7国に分かれていたために、まちまちであった貨幣・度量衡・文字・車輪の幅の統一など様ざまな政策を打ち出し、それを実行していきました。特に文字~書体の統一は重要政策のひとつで、始皇帝は丞相の李斯に命じ、自国で従来使用していた文字(「大篆」)を簡略化し、「小篆」と呼ばれる書体を作ります。これは楷書と古代象形文字との中間的な書体で、現在も印鑑に使われています。なお、始皇帝は、印章一般を指す「璽」を皇帝の印のみに用いるようにも定めています。
子孫が永遠に中国を支配することを願った始皇帝ですが、その死後に二世皇帝となった胡亥には統治能力が無く、また各地で騒乱が生じると、国は統一以来わずか15年で滅亡します。秦に代わって天下を取ったのは農民出身の劉邦で、皇帝となり漢を建てます。漢の敷いた郡県制は、国に長期の安定をもたらします。
秦の時代を代表する美術としては、後の書に影響を与える「小篆」に加え、始皇帝陵に副葬された約8000体の「兵馬俑」に代表される陶磁器だといえます。漢の時代は社会が安定していたこともあり、これに西方文化の影響や官学になった儒教の思想が加わって中国独自の美術様式が生れました。
また秦の公式書体だった「篆書」で書類を書くことは負担になったため、下級役人にも書きやすいよう、篆書を簡略化した「隷書」が普及します。ほかにも行書、楷書、草書などが作られました。そのため「書」が芸術としても意識されるようになります。
秦・漢の時代には目覚ましい文化の発展がありました。その中でも特に注目すべき文化のことや、その時代にいたはずの美術家について見てみましょう。
秦・漢時代の文化において、特に注目すべき点となるのは、「中国全体で文化の統一がなされるようになった」というところです。前述の通り、秦の始皇帝も文字や貨幣などをはじめとした様ざまな面での統一に着手していましたが、それがしっかりと確立し、目に見える結果が大きく出たのが漢時代といえるでしょう。漢時代は前漢・後漢合わせて約400年続き、政治的な統一が長く続けられたことが、文化の統一にも大きく貢献しています。
また、後漢の時代になると、宦官である蔡倫(さいりん)が製紙法を開発し、「紙の文化」が生まれました。紙の文化が無い時代は、木簡・竹簡(木や竹の札)や帛(はく・絹のことを指す)を使っていたのですが、これらは重さや使いにくさがあり、さらにコストもかかっていました。そこに紙の文化が生まれたことで、書写が手軽にできるようになり、文章の伝達スピードが大いに上がったのです。
そして秦・漢時代はさらに、「絵を描く」という文化もかなりの発展を遂げています。紙に書かれた絵画については残念ながらほとんど残っていないのですが、絹の布に書かれた絵画である帛画(はくが)や、漆絵・壁画などは出土によって多くの存在が認められています。
漢時代には、絵画の文化も広まりを見せており、この時代にはすでに絵画の分野で有名となった画人もいたであろう、ということも推測されています。その推測の根拠となっているのは、唐の時代に張彦遠(ちょうげんえん)が著した中国最古の絵画史「歴代名画記」です。この歴代名画記には、漢時代の画人の名もいくつか挙がっているのです。しかし残念なことに、歴代名画記に記された漢代画人の絵画自体は現存が確認できていないため、「有名な画人が居たらしい」ということまでしか言えないのです。
また、作者不明ではありますが、現存する秦・漢時代の美術品の中でも、特に素晴らしいものとして挙げられるのが、後漢時代の墳墓から出土した「馬踏飛燕(飛燕をしのぐ馬)」です。空を飛ぶ燕を踏みつけるようにして疾走する姿は躍動感あふれ、「時の権力者が欲しがった馬とはどんな馬なのか」がひと目で分かる素晴らしい出来ばえとなっています。名そのものは残ってはいないものの、作り上げた作品が2000年後の人たちの心を打つ。そんな美術家が、この時代には確かにいた、ということが分かります。
監修本郷美術骨董館

「やさしく解説!みんなの中国美術入門」は、骨董品買取の専門店として40年以上の実績を誇る本郷美術骨董館が監修しています。
公式HPはこちら