
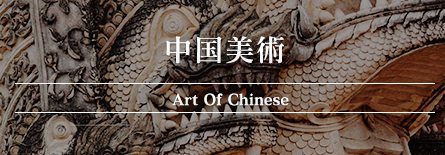
これから中国美術について知っていきたい人から、趣味にしたい人まで。中国美術を学びたい人のためのサイトです。
時代、ジャンル、中国美術を極めたい人向けの記事を豊富に用意しております。あなたが中国美術に触れる際の、お役に立てる入門書となりますように。
このサイトは本郷美術骨董館をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
何紹基は清朝末期の書家で、1799年生まれ1873没の画家・書家です。詩人や学者としても知られています。楷書、行書、草書、隷書に優れていて、特に隷書に力を入れ、「張遷碑」を100回以上も臨書しました。独特のうねりと躍動感が特徴的で今なお多くの人を惹きつけてやみません。
字を子貞、東州居士、猨叟、猨臂翁、晩号は蝯叟と号しています。顔真卿を研究し、蘭、竹、石等の画も有名ですが、書を最も得意とし、清代を代表する書道家としてとして内外の評価を得ています。孫の何維樸も書家として有名です。
40歳頃までの作品です。顔法の向勢の結体や蔵鋒の起筆が顕著でしたが、その後碑学派の影響で北碑に関心を抱き、50代頃から北魏楷書風の要素が見られるようになります。これは、帖学と碑学を融合させる「碑帖兼習」の始まりと言えます。
60代の作品です。何紹基は顔真卿を学びつつ、「横平豎直」の家訓を意識し、篆隷、特に漢隷の学習に打ち込みました。60歳から約5年間「張遷碑」などを臨書し、隷書の筆法を習得。その影響は作品に現れ、表情豊かな書風に変化しました。隷書作品に加え、篆書による款記を伴う絵画も残しています。
何紹基は独自の運筆法から、顔真卿風、北朝楷書風、隷意など様々な要素を含む筆線を自在に操り、高度な技法を駆使しました。最盛期には重厚な書風の作品がありましたが、晩年には枯淡な雰囲気の作品も見られます。しかし、一見力みのない書きぶりでありながら、筆力は終始貫徹し、清朝巨匠の風格を示しています。
監修本郷美術骨董館

「やさしく解説!みんなの中国美術入門」は、骨董品買取の専門店として40年以上の実績を誇る本郷美術骨董館が監修しています。
公式HPはこちら